まいど、あーくんです。
さっきたまたまFIREスレ動画を見ていました。
内容を簡単に言うと、FIREする資産は多分あるけどなかなか踏み切れないという内容でした。
私も同じ(笑)
毎月の定期収入が無くなるのが怖くて踏ん切れないらしい。
確かに私もこの年齢までズルズル仕事を続けたのは、この理由も大きいです。
だってヘタすれば目に見えて資産がズルズル減少していきますからね。
もくじ
★資産と最低収入があれば安定する★
私は2018年頃、資産形成中の資産約2000万円前後の時に精神を患い約1年間の長期療養をしましたが当時はまだ資産が少なく目に見えて減少するのが分かりました。
資産が無くなる恐怖にかられました。
当時はまだ資産額が少なかったことと定期的な収入が何も無いのはやはり恐怖(笑)
この時勉強したのは、FIRE後の資産残高(運用資産)と収入(定期収入)をどうすべきかです。
定期収入(副業)だけでも不安。
要は如何に複数の収入減を確保できるか微妙なバランス感覚。
私の場合は、最低5000万円以上の運用資金とそれとは別に生活防衛資金。※結果、大きく超えてしまいましたが(苦笑)
そして約10万円/月以上の定期収入の確保。
これが出来たら、普通に生活していたら人生逃げ切れるということ。
これは金銭的なこともありますが、精神的な安定感が違いました。
特に定期収入の方。
もし不測の事態が起こってしまった場合、常に最低限の副業のアップデートをしておけばいざという時こちらの方に集中できるからです。
※しかしこれでも少しずつ元本の切り崩しは発生します。
★FIREシミュレーションで徹底的に頭に刻みこむ★
私は様々な角度でシミュレーションを繰り返しました。
①通常モード(4%ルール)
②生活防衛資金多めモード(現金比率が4割近く・利回り減少)
③FIRE開始直後くらいに3割以上のドローダウンモード
④長期インフレモード(2%の恒常インフレ)
⑤長期不況モード(不動産・株式等すべての資産が減少のハードモード)※世界中の株価が20年近く最高値を更新しない場合
⑥想定支給年金が2割減額モード
⑦そしてすべてを組み合わせていくモード
です。
まあ見たらわかる通り私は①番以外はすべてハードモードです(苦笑)
過去の例のほとんどを見ても基本は4%ルールに基づいて、プラスアルファの数年間分の生活防衛資金があればどの年齢でもシミュレーション上では問題無いかと思われます。
私もサイドFIREを目指し始めた最初はそれを基本線にして目標にしました。
ちなみに4%ルールのおすすめ資産配分はこんな感じです。
- 株式:50-75%
- 債券:25-50%(私は定期預金とか個人向け国債とかで良いかと思います)※ここ数年間の債券の安定性に疑問
例えば想定年間生活費が360万円なら、
360万円×25倍=約9000万円(4%ルール)
それと不測の事態に備えて生活防衛資金600万~900万円を加える(普通預金)
みたいな感じです。
これはあくまでも目安です。(日本の税制・インフレ率は米国とは違います)
ただ上記を目標にすることは明確で良いかと思います。
この場合は20歳であろうが、30歳であろうが、40歳であろうが、この運用資金があれば枯渇しない確率は90%以上で大丈夫です。(計算上です)
さらに最大ドローダウン(50%以上の下落)時に運用資金から切り崩さず、生活防衛資金から切り崩せば、より一層成功率が上がります。
過去最大の下落幅だった世界大恐慌時は約3年間かけて何とマイナス86%の下落を記録しました。(現在は金本位制ではないのでお札を刷ったりして何か対処法があるのかもしれませんが・・・)
ちなみに最高値を再更新するまで約15年間かかりました。
なので私は今後も起こらない可能性が高いですが念のために最低でも3年以上の生活防衛資金を確保しています。(それとポートフォリオの10%に抑えて最後の砦ゴールドを積立中)
あと補足ですが、この4%ルールは日本の年金制度は考慮に入れていませんので、年金を考慮すると更に成功率が上がりますし、ハードルも下がります。
★50歳を越えると具体的な想定が楽に出来る★
私はFIREしたいのをグッと抑えて仕事をグダグダ続けて50歳を超えてしまいました(苦笑)
しかし良いこともありました。
50歳を超えると私の場合はですが、ちょっとFIREシミュレーションの見え方が変わり始めました。
それは、
・・・
・・
・
「元本の切り崩しも想定出来ること」
です。
最初は上記では資産切り崩しが「怖い」と書きましたが、年金までの期間15年を切ってくると不思議と資産の切り崩しが想定の範囲内になり始めて徐々に怖くなくなってきます。
FIREのシミュレーションは結局のところ、自分の人生を寿命まで逃げ切れるかに尽きます。
資産を増やすことではありません。
そしてシミュレーションの年齢範囲が広ければ広いほど誤差が大きくなっていきます。
20歳なら90歳までなら残り70年のシミュレーション。
50歳なら90歳までなら残り40年のシミュレーション。
みたいな感じで数字を見たら分かるように少しの入力誤差でかなり大きな金額差が生じます。
しかし50歳以降だと特にですが、65歳からの年金支給額の具体的な金額が想定出来るようになっていきます。
今後数年間の収入状況や今後の大きな支出がどれくらいになるのかある程度具体的に想定できます。(50歳以降大きな逆転サヨナラホームランもしくはサヨナラ負けはほぼ無いと見ています)
それともし今後年金制度が改悪することがあっても急に改悪することはほとんどありません。
理由は過去の制度改正(改悪?)を見ればわかります。
一気にやらずに年月をかけて徐々に支給金額を下げたり、支給年齢を上げたりしています。
なので今後も改正があるでしょうが、「明日からいっきに5万円減額」とか「明日からいっきに全員70歳支給」みたいなことはありえません。(もしあればそれはもう完全に年金制度が破綻した場合のみです)
なので私は40歳前半時までは4パーセントルールに基づいた資産運用を目指していましたが、特に50歳以降は資産切り崩しを想定したシミュレーションがメインとなっております。
4%ルールに基づき資産を残すというよりも安定的に定額切り崩していく方法へチェンジです。
生活費は各家庭それぞれなので一概には言えませんが、私で言えば50歳時点で完全FIREで最低でも7000万~8000万円以上です。
これは資産を残すというよりも元本の切り崩しが前提でのシミュレーションです。
しかもかなり厳しく見積もっています。
利回りを厳しくしているのもそうですが、65歳前後で徒歩圏内ですべてが揃う場所(役所・病院・外食・商店街など)へマイホームを買い替えたり(賃貸も)とか、人生最後は老人ホームに入居するとか結構お金も使うシミュレーション内容です。
安定度を保ちつつ、死ぬときはお金をなるべくゼロに持っていきたいので・・・。
私の両親を見ていても年齢を重ねれば重ねるほど、生活費が激減しています。
あとこれはとても大事なことですが、税制・社会保険料などの無知は無駄な節約を生んでしまう可能性があります。
どれくらいかかるのか分からないから、逆に怖くて必要以上に備えてしまう。
素人レベルでもいいので常にアップデートだけは欠かさずやっておくべきですね。
今は便利な時代で専門家が無料で新しい情報を公開してくれています。(良い時代になったもんです)
年齢を重ねると、資産を増やす努力よりも減らさない・長持ちさせる方に労力を割いたほうが得策だと私は最近とても感じています。
リスクをそこまで取っていかなくても良いかと思います。
★結局は資産額の多さ★
FIREするのが不安なのは4%ルールがどうとか、定期収入がどうとか、切り崩しがどうとかではなく、結局は金融資産の保有量。
どこをどう切り取っても死ぬまで資産が枯渇しない次元に達していたら何も問題ない。
これまでの話はあくまでも方法論です(苦笑)
結局資産が枯渇するんじゃないかと常に不安になるのは、「資産額が少ない」ということです。
FIREを目指している人は必ずと言っていいほど、何度もシミュレーションをしているはずです。
その時にギリギリラインでFIREするから不安なのだと思います。
結局は資産額。
不安だからと言っていつまでも資産を増やし続けるわけにはいかない。
取り戻すことが出来ない残された人生の時間が最も大切。
それらのバランスが上手くいったときがFIREへの道が開ける・・・のかな。
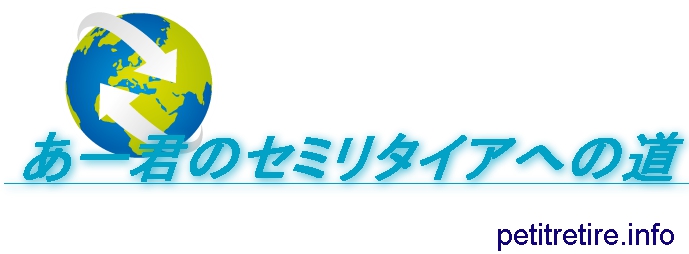
コメント
コレばっかりは実行しないと解らないのも無理からぬ話ですが
意外と収支均衡が図れますよ。
税制、社会保険の最適化は本当に1年で結果が全うと解りますね。
何もせず言われるママに納めても受けるサービスは同じ…
ソレを知らないと本当に大損です。
>黒田様
いつもありがとうございます。
何度もシミュレーションしましたが、結局は分からない(苦笑)
都度条件が変わってきますので実際にやってみてどれが最適なのかを探り探りでやっていこうと思います。
言われる通り、受けられるサービスは同じなのでよく考えて行動しないとですね。
「結果が全く違う」でした